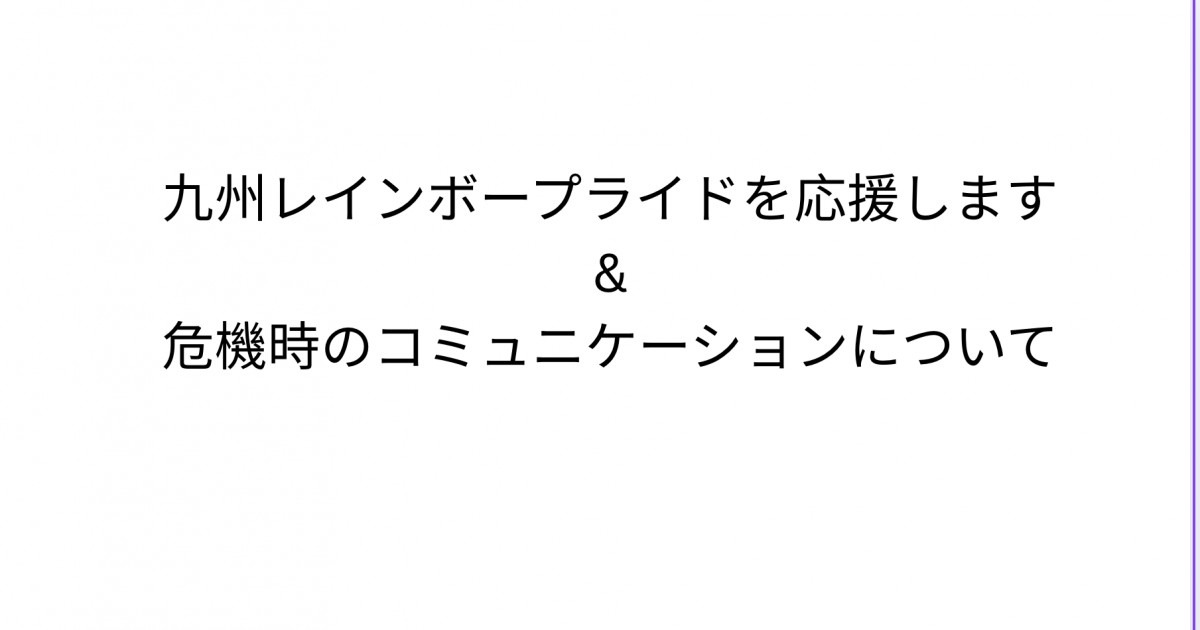映画『ブルーボーイ事件』とトランスの人たちと医療の現在
映画『ブルーボーイ事件』が先週公開となり、話題になっている。この作品は、実際に1960年代に日本で起きた事件を題材としていて、いわゆるトランスの人々(当時はそのような言葉はなく、現在もなお当事者が自身を指し示す言葉は多様だが、いったんこの言葉で統一する)が生きのびることが今よりも過酷だった時代を活き活きと描写している。
ブルーボーイ事件は、トランスの人々にとっては超有名な事件だ。この手のテーマを扱った本には必ず登場する出来事といっても過言ではない。昔は性別適合の医療を公に受けることすらできず、事件以降は医療がアングラ化し、なんとか90年代になって「性同一性障害」という名前ができて「病気」ということにして正式な扉が開かれていった。映画では、主人公サチが、昼間の仕事をしているからという理由で裁判の証言者になって欲しいと頼まれる場面があるが、のちに公式に「性同一性障害の治療」が登場するようになった時に、ニューハーフや夜の商売をしている人は除外すべきとの議論が行われたことにも通じる。医療行為が「まっとう」であることを示すために、いろんな戦略が使われた。病気としての打ち出し方を含め、後世の人間からしたらグロテスクに映るものもある。
ブルーボーイ事件は当事者にはよく知られた話だったが、世間では無名の出来事だっただろう。ある人たちの歴史に想いを馳せることは、その人たちへの社会での敬意を高める効果がある。当事者の一人として、古い時代を生きたトランスの人たちの物語に触れる機会が、今後も増えていったらうれしい。
※このニュースレターは無料登録した人のみ読める記事も今後用意しています。ご登録がお済みでない方はこの機会にぜひ宜しくお願いいたします。
今も続いている医療資源の不足
映画を見て、今も変わらないなと思うことがたくさんあった。
その一つが、手術を受けるためにサチが病院を探して苦労するシーンだ。電話帳をひろげて、産婦人科に片っ端から連絡しては断られる。今でも、ホルモン療法ができる病院を探すために同じことをしている人たちがいる。トランス男性である監督自身が周りから聞いたり、自分で体験したことなのではないかとも思う。
ホルモン療法は外見を男性化ないし女性化するために必要で、さらには生殖腺の摘出手術を受けた人は健康を維持するためにも欠かせないものだが、近所でやってくれるところをなかなか見つけられない人がいる。仕事をしている人が2〜3週間ごとなど定期的に打つとなると、近所にないと不便だ。実際に、私の友人で、地方への転勤を命じられたがホルモン治療の継続が困難であったため転職した人もいる。このような場合に職場とどう調整したら良いか、以前弁護士に依頼してQ&Aを作ったことがあるぐらいだ。
ホルモン療法や性別適合手術を受けるには、90年代以降は専門の精神科医により診断を受けることがガイドライン上求められている。ただ、このような「ジェンダークリニック」は2025年現在も関東でも数カ所、東北地方で一つあるかどうかの状況だ。地方在住者は、診断書をもらうために高速バスや新幹線などで何度も通院を行う必要がある。地域によっては初診の予約が取れるのかは抽選だ。
性別適合手術は、通常はホルモン療法の後に行うことになっているが、この二つの組み合わせを行うと保険の適用外とみなされるため、手術の内容によるが治療費も数十万円〜数百万円程度かかる。トランスの人たちの中には経済状況がよくない人も多く、工面するのも大変だ。
安全かつ当事者のための医療へ
このような環境で、トランスの人たちはしばしば安全ではない医療機関に追いやられた。2012年には歌舞伎町の個人診療所で乳房切除の手術を受けた若者が、手術中に死亡している。当時、他の病院では乳房切除を受けるには60万円程度かかったが(クリニックにもよる)、この病院ではキャンペーンと称し25万円という破格での施術だった。手術は慣れない医師が一人だけで行っていた。
またジェンダークリニックについても、遠方から通院する時間、金銭、心理的余裕のない当事者らを中心に、即日で診断書を出す病院がネットの口コミなどで知られ、医療行為としての妥当性やモラルが疑われる状況が生じている。
状況を改善するために、日本GI(性別不合)学会は認定医制度や認定施設制度を作り、安全性や医療技術、倫理観などを備えた医療の担保に取り組んでいる。乳房切除の手術についても、以前は日帰り手術で、ドレーンがついた状態で病院の近くのホテルに宿泊する人が多かったのが、入院して行うことが増えていった。ホルモン療法をしていない人が乳房手術を認定施設で受けるときには保険が適用されるようになり、安全面だけでなく経済的なメリットもある。
一方で、さまざまな理由でガイドラインにはよらず、診断は受けずにホルモン療法や手術を希望する人もいる。現在も、性別適合手術の約半数は国内ではなくタイで行われている。その方が技術・コスト・時間的にメリットが大きいと考える人が多いからだ。また、そもそも自分を病気だと思っていない当事者にとっては、精神科医を訪れて、いまさらわかりきった自分の性のあり方について説明すること自体がナンセンスと感じる人もいる。
The New Yorkerが作ったショートフィルム「Script」では、トランスの人たちが医者と対峙する時のストレスについて扱っている。私も運営に関わっているトランスジェンダー映画祭でも以前上映した。YouTubeにも全編上がっていて、自動翻訳で日本語字幕も選べるのでよければ観てほしい。この映画では、当事者たちが医師役、患者役をそれぞれ演じる。
トランス男性であれば男らしく、トランス女性であれば女らしく、自分の人生をそれらしく振りかえらなければならないことや、「トランス男性なら、もっと筋肉つけたいんでしょ」などの決めつけににうんざりしている当事者の本音がそこでは語られる。
「本当のところ、診断のプロセスにうんざりしている」「医者が求めているステレオタイプの物語を知っているが、それは私のしてきた経験とは違っていた」などと当事者は語り、自分たちが医療提供者だとしたら、どのように相手と接するのかを演じる。より良い医療のあり方を模索する試みである。
今なお、トランスの人たちが安心して、安全に医療にアクセスできる状況は担保されていない。映画『ブルーボーイ事件』をきっかけに、トランスの人たちに関心を持つ医療関係者が増えて、より良い未来を一緒に作ってくれることを願う。
すでに登録済みの方は こちら